日本の国土の約7割は森林で覆われており、河川の水源地となっています。降水として森林にもたらされた水は、一部は蒸発・蒸散によって大気へ返され、残りの水が下流域へ流出します。このような水の循環を調べる学問を水文学(すいもんがく)と言います。
水文学の視点を持つと、
森林の様々な働きとそれらのつながりが見えてきます。
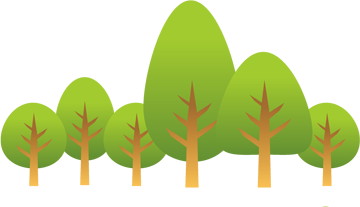
123
例えば、雨が林床に到達し森林土壌に保持されることによって、降雨時の急な出水を抑え、逆に無降雨時には水をゆっくり下流域へ供給する働きがあります。また、光合成によって植物の葉の気孔から二酸化炭素が取り込まれる際、蒸散が行われるため、植物の水利用は二酸化炭素吸収にも密接に関わっています。他にも、水が下流域へ流出する際には、土砂や栄養塩を運ぶ働きもします。
このように、森林の様々な働きには「水」が関わっており、水文学の視点を持つことでそれらのつながりが見えてきます。私たちは「水」をキーワードに、森林の様々な働きを読み解く研究を進めています。
123
123